先日伺った射水市での小さいながらも強烈な光りを放つ取り組みを見て、国の掲げる「地方創生2.0・関係人口」がなんかモヤつく。。。
ということで少しnoteでまとめてみた。
–■地方創生2.0の誕生–
●「関係人口」の登場
地方創生施策の刷新を目指して登場したのが、当時の石破茂地方創生担当大臣が主導した「地方創生2.0」である。これは、第一次安倍政権下において展開された「人口維持・インフラ整備・東京一極集中の是正」といった政策アジェンダの次フェーズとして位置づけられたものであり、政策の中心的キーワード・KPIが「関係人口」へとシフトした。
「人口維持」や「東京一極集中の是正」がさすがに無理ゲーだと感じたのだろうか、リアルな数としてではなくほんわかした・曖昧な「関係人口」。経済波及効果とも同じ臭いを感じるなんとも行政らしい概念・用語であり、コンサルの鉛筆ナメナメや行政のご都合主義でなんとでも動かせる数字でもある。
地方創生1.0(←そういう言い方で良いのかな?)でも「移住・定住」は、こども医療費・給食費等の無料化、PFI法のBT(サービス購入型)のほぼ建売住宅に近い各種報奨金等のついた移住・定住住宅の建設等の「表面的な人口の奪い合い」でしかなかったことが、上記の資料等でも明確に書いてある。
当初目指していたはずの地方創生1.0は「それぞれの自治体の人口の絶対数」にフォーカスを絞ったこともあり、残念ながらうまく機能してこなかった。
KPIの設定方法、各自治体の表層的・短絡的な人口の奪い合い政策はふるさと納税と同様に意味のあるものではなかったが、ごまかしの効かない「絶対数」をKPIとした点ではまだマシだったのかもしれない。
同時に、絶対数がKPIになったからといって数字だけを取り繕うために本質・根本的な課題解決から目を背け「右から左に動かせば良い」と血眼になってしまうのはあまりにも経営感覚が欠如していたことは忘れてはならない。(ただ、内閣府としてこうした不都合な真実・結果を総括をしたことは素晴らしいと思う。過去にはCCRC、ふるさと創生等、チカラこぶ入れていたはずの政策がいつの間にかフェードアウトしているものが山ほどある。公共施設マネジメントもそんな感じ)
地方創生2.0では、こうした背景もあって「関係人口」がスローガンが掲げられ、都市部と地方をつなぐ“ゆるやかな関与”の担い手が、国の視点で見たら「地方の新たな支え手」として期待されることとなり、一般市民や地方公共団体、地域プレーヤーから見たら実情に構うことなく過剰な役割・期待を担わされるようになった。
●地方創生伴走支援制度
国は、こうした流れを受けて各府省庁に所属する官僚を地方自治体に「地方創生支援官」として派遣し、現場支援を通じて地域経営を担う人材を供給するスキームも整備した。2025年度現在、180名/60チームが市町村へ派遣されているらしい。
ただ、冷静に考えればこのような仕組みを用いずとも、これまで国は副市長や各部長などのポストで地方公共団体に直接どっぷりと浸かる形で職員を出向させており、わざわざ新しい仕組みを用いる必要があったのか問題も存在する。(正確な人数は把握していないが、今回の仕組みの180名より圧倒的に多くの職員が各自治体に入り込んでいるはずだ。)
国はこのような制度で地方が直面する困難な状況に対応できると本当に思っているのだろうか。
派遣業務が「副業」として位置付けられ、「勤務時間の1〜2割程度」の業務範囲内で「1時間/週程度のオンライン会議」、「3回/年程度の自治体訪問」をするだけでは、担当者の顔を覚えるぐらいで、どのようなメンタリティで活動しているのかすらわからないのではないか。その自治体の空気・歴史・文化・風土もわかることはないだろうし、ましてや地域コンテンツ・地域プレーヤーと触れる機会もほぼないだろう。しかも「助言等の支援」がベースであることからも、地域の1プレーヤーとして「自ら動く」ことは想定していないようだ。
支援官が具体的な政策形成・事業計画の伴走支援にまで本気で深く関与するためには、地方との継続的・地道な信頼構築と現地課題への深い理解が不可欠であるが、このような業務の隙間時間を活用した片手間の「ちょっとお邪魔します」型ではとてもそこに及ばないだろう。
このような形で入っても、所詮できるのは抽象的・一般論や国の大好きな「優良事例の横展開」の紹介にしかならず、議論もこうあったらいいな・多分こうなるだろうの「抽象的な空中戦」に留まるだろうし、それは現場をやらない学識経験者を中心とした有識者委員会とも大した差が出てこない。
===続きはリンク欄「まちづくり公式note」===
https://note.com/machimirai/n/n5780acf2b21d
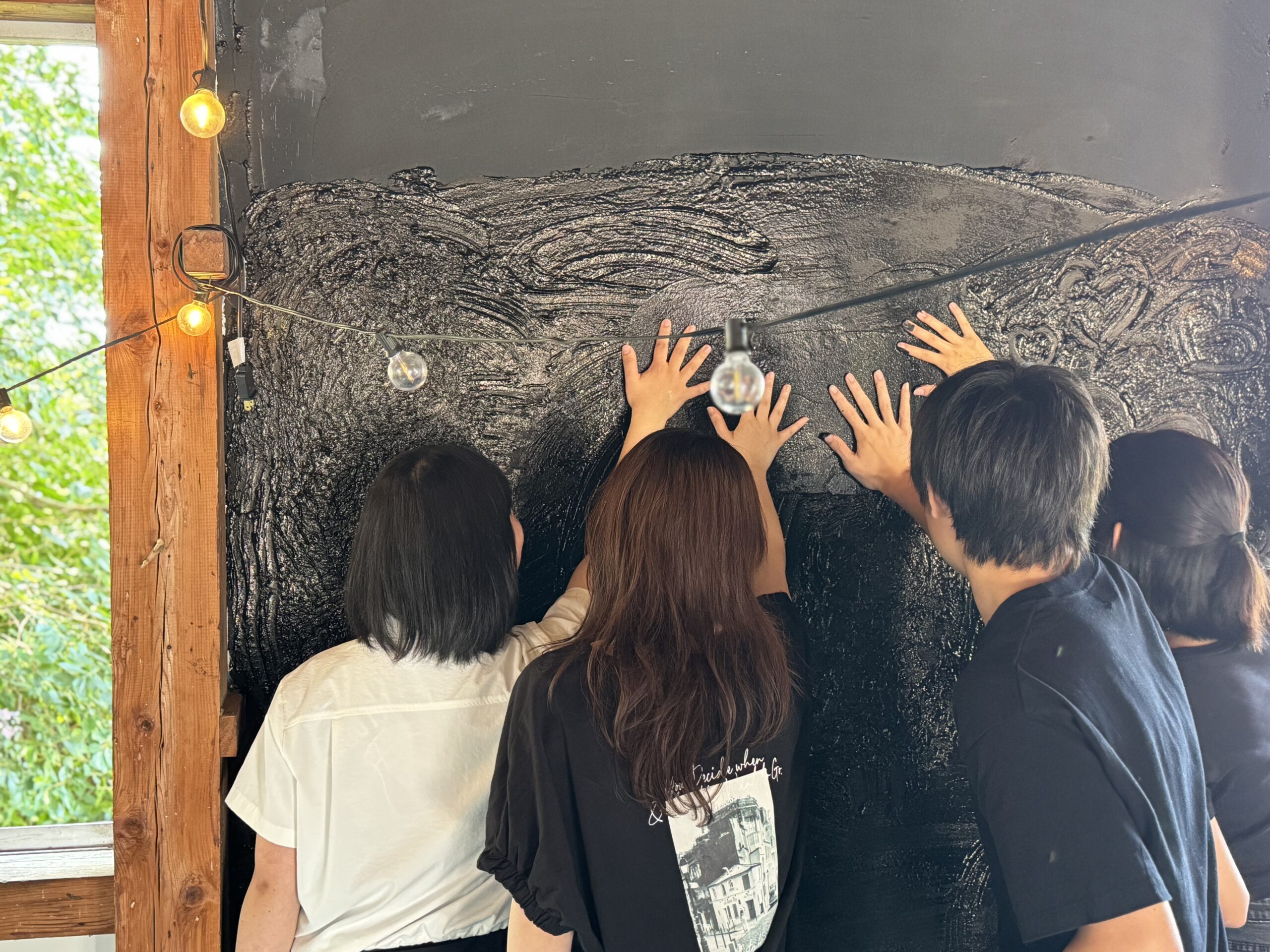
Comments are closed